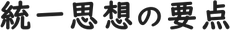神性-心情
「心情」とは何か
「心情」とは何かと問われれば、色々な答えがあるかもしれませんが、統一思想または統一原理において心情とは、「愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動」です。
なお、ここでいう「愛」とは、自己中心的な愛ではなく利他的な愛、「真の愛」です。
文先生は「真の愛」について以下のように話されておられます。
「受けようという愛ではなく、人のために、全体のために先に与え、ために生きようという愛です。
与えても、与えたということすら記憶せず、絶えず与える愛です。
喜んで与える愛です。
母親が赤ちゃんを胸に抱いてお乳を飲ませる喜びと愛の心情です。
子女が父母に孝行して喜びを感じる、そのような犠牲的な愛です。」
また、先の「情的な衝動」とは、内部からわきあがる抑えがたい願望または欲望を意味します。
普通の願望や欲望は意志で抑えることができますが、情的な衝動は人間の意志では抑えられないのです。
欲望は達成されてこそ満たされます。
しかし大部分の人間にとって、喜ぼうとする欲望が満たされないでいるのは、喜びは愛(真の愛)を通じてしか得られないということが分かっていないからなのです。
そして喜びが愛を通じてしか得られないのは、その喜びの根拠が神様にあるためなのです。
神は心情である
神は心情すなわち愛を通して喜ぼうとする情的な衝動をもっておられますが、そのような神の衝動は人間の衝動とは比較にならないほど抑えがたいものだったのです。
人間は相似の法則に従って創造され、そのような神の心情を受け継いだので、たとえ堕落して愛を喪失したとしても、喜ぼうとする衝動はそのまま残っているので、情的な衝動を抑えるのは難しいのです。
ところで神において、喜ぼうとする情的な衝動は、愛そうとする衝動によって支えられています。
真の喜びは真の愛を通じなければ得られないためです。
したがって、愛そうとする衝動は喜ぼうとする衝動よりも強いのです。
愛の衝動は愛さずにはいられない欲望を意味します。
そして愛さずにはいられないということは、愛の対象をもたずにはいられないということを意味します。
そのような愛の衝動によって喜ぼうとする衝動が誘発されます。
したがって愛の衝動が一次的なものであり、喜ぼうとする衝動は、実は愛そうとする衝動が表面化したものにすぎないのです。
ゆえに神の心情は、「限りなく愛そうとする情的な衝動」であると表現することもできるのです。
愛には必ず対象が必要です。
特に神の愛は抑えがたい衝動であるため、その愛の対象が絶対的に必要だったのです。
したがって「創造」は必然的、不可避的であり、決して偶発的なものではなかったのです。
このように心情を動機として宇宙創造の理論「心情動機説」は創造説が正しいか生成説が正しかという一つの現実問題を解決することになるのです。
心情と文化
神の性相は内的性相と内的形状から成っていますが、内的性相は内的形状よりもより内的で、心情は内的性相よりもさらに内的です。
このような関係は、創造本然の人間の性相においても同じであり、心情が人間の知的活動、情的活動、意的活動の原動力となることを意味しています。

すなわち心情は情的な衝動力であり、その衝動力が知的機能、情的機能、意的機能を絶えず刺激することによって現れる活動が、まさに知的活動、情的活動、意的活動なのです。
人間の知的活動によって、哲学、科学をはじめとする様々な学問分野が発達するようになり、情的活動によって、絵画、音楽、彫刻、建築などの芸術分野が発達するようになり、意的活動によって、宗教、倫理、道徳、教育などの規範分野が発達するようになります。
創造本然の人間によって構成される社会においては、知情意の活動の原動力が心情であり愛であるがゆえに、学問も芸術も規範も、すべて心情が動機となり、愛の実現がその目標となります。
ところでこれらの「学問、芸術、規範」の総和、すなわち人間の知情意の活動の成果の総和が文化なのです。
したがって創造本然の文化は心情を動機とし、愛の実現を目標として成立するのであり、そのような文化は永遠に続くようになります。
そのような文化を統一思想では「心情文化」と呼びます。
しかしながら人間始祖の堕落によって、人類の文化は様々な否定的な側面をもつ非原理的な文化となり、興亡を繰り返しながら今日に至っています。
これは人間の性相の核心である心情が利己心によって遮られ、心情の衝動力が利己心のための衝動力になってしまったからです。
そのように混乱を重ねる今日の文化を正す道は、利己心を追放し、性相の核心の位置に心情の衝動力を再び活性化させることによって、すべての文化の領域を心情を動機として、愛の実現を目標とするように転換させることなのです。
すなわち心情文化、愛の文化を創建することなのです。